こんにちは、Kanotです。2021年現在、世界で最もイノベーティブなサービスが生まれている場所として、真っ先に名前が上がるのは、やはりアメリカのシリコンバレーですよね。
(といいつつ、最近はやたらと巨大企業による買収・模倣が相次いだり、プライバシーやビジネスモデルの問題があったりと、正直シリコンバレーいまいち感はかなりあるのですが、今回のお題とはずれるので、その話はまた今度にします。)
「そのシリコンバレーがなぜイノベーションが起きやすい場所になったのか」について書かれた本を読んだので、読後メモとして紹介したいと思います。読んだのは、カリフォルニア大学バークレー校のサクセニアン教授が書いた「Regional Advantage」という1996年に発売された本です。「現代の二都物語」として日本語訳版も出ているようですが、米国にいるため、今回は中古が安く手に入った原著を読みました。
アフリカのイノベーションとかを研究対象としてる関係で、先進国のイノベーションについても調べてるうちにこの本にたどり着きました。1996年出版と、かなり古い本ではあるので、どちらかというと自分用のメモです。もしこれを読んで興味を持った方は、(日本で買うと高いので)図書館などで邦訳版を探してみるといいかもしれません。
ボストン vs シリコンバレー
さて、この本は邦題が「現代の二都物語」となっているように、二つの都市を比較しています。一つはカリフォルニアのシリコンバレー、そしてもう一つはボストンのルート128です。
この2つの都市は、1960〜1970年代に一大ビジネスとなった半導体ビジネスで成功した地域で、アメリカでも将来を期待されるIT産業地域として注目されていました。そして、アメリカの東海岸を代表する都市であるボストンにはMITがあり、西海岸のシリコンバレーにはスタンフォード大学があり、産学連携が取れるという共通点がありました。それが、結果としてはシリコンバレーの圧勝、ボストンはイノベーションの聖地にはなれませんでした。
それはなぜだったのか?どのような違いがあったのか?それを双方の関係者へのインタビューなどを通じて紐解いたのが本書です。
組織のボストン、個のシリコンバレー
では、どのような違いがあったのでしょうか。ここでは、以下のキーワードでざっくり比較してみます。(ボストンを赤、シリコンバレーを青でハイライトしてみます。)
- 組織(大企業)のボストン、個(スタートアップ)のシリコンバレー
- 国・軍との関係
- 競争とコラボレーション
- 失敗を許容する文化
1960〜1970年代の半導体がブームだった頃、ボストンでは半導体の大企業が複数誕生し、非常に強い力と影響力を持っていました。一方のシリコンバレーは、HP(ヒューレット・パッカード)などを皮切りに同じく半導体を主軸とする様々な企業が生まれていきますが、小さいスタートアップも非常に多い環境であったそうです。
そのような環境下で産業がどのようになっていったかというと、ボストンでは大企業が自分の力でイノベーションを起こすことを目指し、シリコンバレーは人・会社がコラボレーションする形でイノベーションを起こすことを目指したのです。
これが両都市の環境の違いとして明確に分かれていきます。
ボストン
ボストンは、自立できる大企業が多くありました。それにより、大企業が産業の主要部分を支配してしまったため、スタートアップが入り込む隙がなく、中小企業があまり育ちませんでした。
また、東海岸という土地柄、国や軍からの距離も近く、顧客に多かったため、官僚組織にマッチしやすい大企業が好まれたというのも、このような産業構造になった理由の一つだったようです。
シリコンバレー
シリコンバレーはスタートアップ中心の産業地域であったため、非中央集権型の産業構造で、競争は厳しいもののコラボレーションも多く発生する文化でした。
まず、転職に非常に寛容で、何回転職したかを笑いながら話し合うなど、近くの競合他社に転職することも全く問題ありませんでした。(駐車場を変えずに会社を変えるのもよくある話だったとか。)
また、企業のサイズも小さいため、近隣企業とのコラボレーションも多く発生していました。そして、例え起業して失敗しても、それをマイナス評価しない文化に繋がっていきました。それによって、どんどん新しい事業にチャレンジできる文化に繋がったようです。
おわりに
本にはもちろんもっといろんな情報があるのですが、超ざっくり解説ですみません。要点の要点ということで・・。
いずれにせよ、こういった環境差が続いた結果、ボストンは半導体ブームの終わりとともに下火になり、シリコンバレーはご存知の通り、その後イノベーションの聖地として一斉を風靡することになります。
はてさて、ここでの学びは他の国や地域でも生かすことができるのでしょうか。少なくとも、スタートアップを成功させるための産業構造に関するノウハウをネットなどで検索すると、シリコンバレーの成功体験を元にしたものがほとんどです。失敗を許容する文化や、成功者がエンジェル投資家となって次世代支援をするなどですね。
一方、ボストンの話を読んでいると、どうしても今の日本の大企業の姿と重ねてしまうのが正直なところです。
このどちらが正しい産業構造なのかは、今後シリコンバレーがこのままイノベーションの聖地として栄え続けるのか、様々な限界により別の聖地が生まれていくのかによって(後付けで)教訓は変わっていくのだと思いますが、現時点でアフリカなどでイノベーションを考えると、まずはシリコンバレーから学ぶべきことが多そうですね。
そして、スタートアップとかイノベーションとか、一見最先端ですが、こうやってたまには歴史を振り返ってみるのも面白いですね。

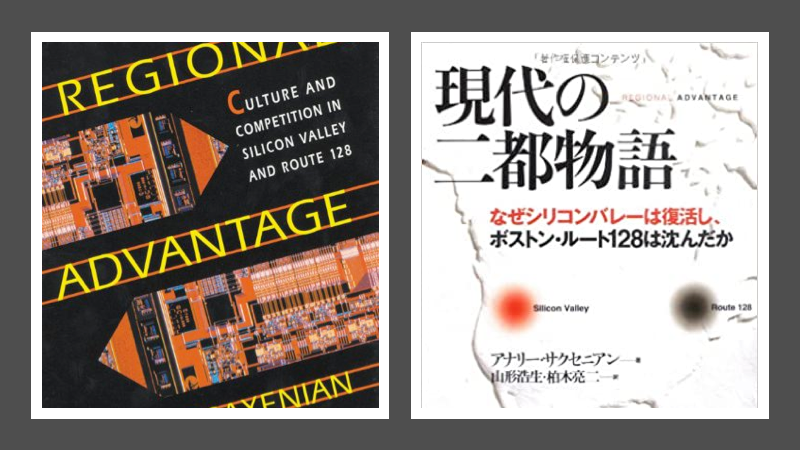


コメント
ボストンのMITといえばメディアラボ。2016年当時でありますが、メディアラボからスピンオフした30のプロダクトやプラットフォームが挙げられています。
https://www.media.mit.edu/files/30-in-30.pdf
1986年の創立以来(今の価値で)10億米ドルを超える潤沢な予算が突っ込まれ、コネを駆使してかき集めた才能の割には…ビジュアルアート志向が強くて上品でハイブローでオサレでニッチだけど浮世離れした…浄土かよ!という感じがします。
ジョンマエダさんとか、アーティストとして個人で完結していて、傍目から見れば超高学歴の果てに悟りに達した人みたいだもんなあ…。
かたやシリコンバレーは多くの映画やドラマのネタにもなってますね。それこそ数十年程度の歴史の中でも面白いストーリーがたくさん掘り起こせ、バランスもへったくれもない俗な世界、娑婆(シャバ)という言葉で表現できるような。
とりとめのない文章でした。
Ozakiさん、コメントありがとうございます。
確かにメディアラボはなんかキラキラしすぎちゃってる感じもありますね。
一方のシリコンバレーは良くも悪くもこだわりないというか、マッチングアプリだろうがなんだろうが売れりゃいい、みたいいな俗な世界ですよね(笑)。